「残間里江子って何してる人?」そう疑問に思った方は多いのではないでしょうか。
テレビや雑誌で名前を目にした事もあまりなく、どんな活動をしているのかは意外と知られていません。
残間里江子さんは、雑誌編集者や出版・イベント・文化事業まで幅広く活動してきました。
本記事では、残間里江子さんのこれまでの仕事や、誰をプロデュースしてきたのか、そして現在は何をしているのかをわかりやすくまとめます。
残間里江子って誰?

残間里江子(ざんま りえこ)さんは、1950年3月21日、宮城県仙台市に生まれで、2025年8月現在、75歳です。
明治大学短期大学(法律科)を卒業された後、静岡放送(SBS)のアナウンサーとしてキャリアをスタートされました
アナウンサーを務めた約2年半後、雑誌記者や編集者へとキャリアチェンジ。
光文社「女性自身」での編集や、平凡社の雑誌『Free』編集長も務められ、独自の視点や編集手腕で注目を集めました
1980年には、企画制作会社「株式会社キャンディッド・コミュニケーションズ」(キャンディッド・プロデュース)を設立しました。
出版や映像、文化イベントなど、多彩な分野でプロデュースを手がけるようになります
1986年には「地球は私の仕事場です」、1991年には「21世紀への伝言」、2001年には「大人から幸せになろう」といった、大型トークセッションを自主企画として開催。
栗原はるみさんや小泉総理(当時)などを多くの著名人をパネリストに迎えたイベントを開催し、社会的な反響も大きかったようです
残間里江子さんは“アナウンサー”“編集者”から“プロデューサー”“文化発信者”“社会ネットワーク創設者”まで、多様な顔を持ち続けるマルチな活動家です。
誰のプロデュース活動をやっていたの?
残間里江子さんはプロデューサーとしてもすぐれた能力を発揮してきました
その代表的な一つに、山口百恵さんの自叙伝 『蒼い時』のプロデュースがあります。
若きアイドルとして国民に愛された山口百恵さん。
1980年、その引退に際して発表された自叙伝『蒼い時』を出版プロデューサーとして手がけたのが残間さんです。
自伝にはゴーストライターを使わず、百恵さん自身が言葉を紡いだことを公表。
「自分の思いを発信したい」という意思を最大限に尊重し、残間さんがプロデュースし、多くのファンや読者の胸を打ちました
その他にも残間さんが手がけたプロデュースで印象的なのは『愛・地球博(2005年)誘致の総合プロデューサー』です。
2005年、日本の顔とも言える国際博覧会「愛・地球博」の誘致総合プロデューサーに就任。
当時、大きな話題を集め、国内外の注目を集めるプロジェクトとなりました。
残間さんの緻密な調整力と文化への理解が、誘致成功への1つとなりました。
残間さんの企画力や、創造力は参加者をいつも魅了してきました。
「クラブ・ウィルビー」とは?
「クラブ・ウィルビー」とは、2009年、残間里江子さんが「新しい日本の大人文化」を創造するというビジョンの元に誕生しました。
既存の“シニア”像を払拭し“大人”という言葉に新たな輝きを与えることを目指した、会員制コミュニティです。
このクラブの魅力は、単なる交流の場ではないこと。
セミナー、勉強会、ツアー、時には「ウィルビー混声合唱団」での合唱など、知的好奇心を満たすさまざまな企画が目白押しです。
さらに社会貢献活動にも積極的で、メンバー同士が“豊かな大人であること”を共に感じ、築いていく機会が多彩に用意されています
残間さんによれば、現在の70代前半はかつての若者世代と同様、音楽や映画、旅に触れて心を揺さぶられた世代。
そんな大人たちが、自分のスキルや経験を“社会に還元したい”と考えている——その思いに応える場こそが、クラブ・ウィルビーなのです。
特に、若い世代との「クロスジェネレーション」交流に注力し、世代を超えた対話の場を設けるイベントにも積極的なようです。
日本郵政とのコラボ企画として、クラブ・ウィルビー代表・残間さんが安藤優子さん、椎名誠さんと共に「手紙の魅力」について意見交換するなど、アナログ文化の温かさを再発見する語り合いが、多くの共感を呼びました
残間さんが設立したクラブ・ウィルビーは、ただの“サロン”ではなく、「大人だからこそできること」をめいっぱい楽しみ、学び、つなげていく場です。
残間さんと行政や公共機関とのつながりとは?
残間里江子さんは、雑誌やイベントのプロデュースにとどまらず“大人の文化”を形作るリーダーとして、行政とも深く関わってきました。
まるで社会と文化の架け橋をつなぐナビゲーターのように、政策の裏側にもそのセンスとバランス感覚を発揮しています。
主に関わってきた行政機関・委員会(一部ご紹介)
- 国土交通省「社会資本整備審議会」:インフラや都市づくりに関する政策の議論に参加
- 財務省「財政制度等審議会」:国の財政改革を議論する場で助言を提供
- 法務省「裁判員制度に関する検討会」:一般市民の裁判参加制度についての検討にも携わる
- 内閣府「男女共同参画推進連携会議」:社会での男女平等推進に向けた施策に関わる
- 総務省「定住自立圏構想研究会」:地方の定住促進と地域活性を考える場にも関与
- 国土交通省「地域づくり表彰審査会」:地域づくりの優れた活動を表彰する審査にも参加
など、様々な場に参加してきました
残間里江子さんの名前を聞いたことはなくても、あなたの生活する何かに残間さんは貢献してきました。
残間さんが出版した書籍たち
豊かな人生経験と社会への視点が光る、残間里江子さんの著書をいくつかピックアップしてご紹介します。
『人と会うと明日が変わる』(イースト・プレス、2011年)
「人と会うこと」の価値を深く洞察したエッセイ。
携帯やネットで繋がる時代だからこそ、直接会う意味を問い直しています。
日常と人生にささやかな変化をもたらすヒントが詰まった一冊です。
『それでいいのか 蕎麦打ち男』(新潮社、2005年)
団塊世代に向けたエールとも言える一冊。
人生の新たなカタチを探る「蕎麦打ち男」の姿を通して、成熟世代の自立や再出発へのヒントを描いています
『もう一度花咲かせよう 「定年後」を楽しく生きるために』(中公新書ラクレ、2019年)
“定年後の人生をどう豊かにするか”がテーマの新書。
人生100年時代における再び咲くヒントが、残間さんの温かなエールとして詰まっています。
残間里江子さんの著書は、人生の節目を迎える読者に寄り添いながら、「会うこと」「自分を再発見すること」「人生を輝かせること」に焦点を当てています。
読者の共感を呼び起こし、「次の一歩を踏み出したくなる」ような優しい力を持つ残間さんのメッセージが、各書籍に込められています。
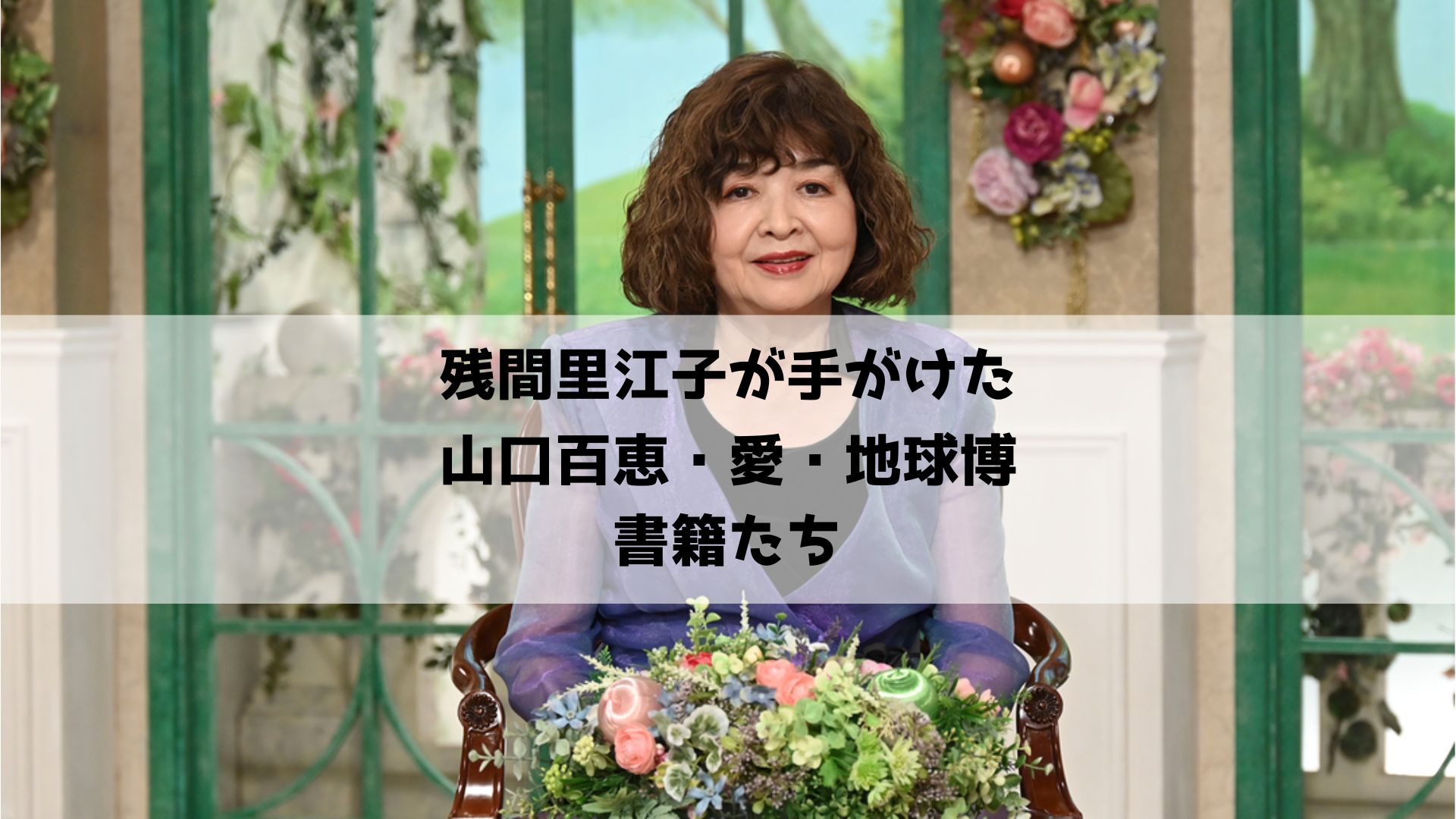


コメント